
ポイント
2024年1月
7分36秒


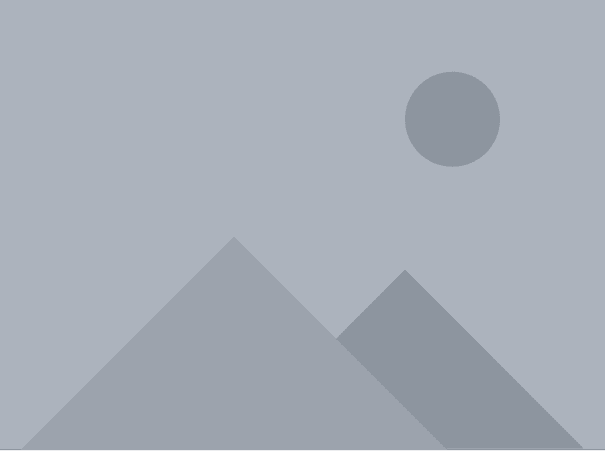
フローチャート2
| 便の性状 | 便の性状の記載には、ブリストル便形状スケール※(国際学会で定められた尺度)を活用します。便の性状は表現しにくく、人によって異なる可能性がありますが、スケールを使うことでスタッフ共通の尺度で把握することができます。ブリストルスケールの1・2は便秘、3〜5は普通便、6・7は下痢と考えます。 ※Lewis SJ, et al.: Scand J Gastroenterol 1997; 32(9): 920-924 |
| 便の量 | 便の量は、うずら卵大、あるいは〇cm×〇cm〇本といった具体的な表現にできると詳しく判断することができます。施設で統一した基準を設けるとより記載しやすいでしょう。 |
| 排便時間 | |
| 便失禁の有無 | |
| 随伴症状 | 腹痛や出血の有無などを記載します。 |
| 排便の方法 | |
| 誘導の有無 | |
| 下剤の種類と量 | 投与時間と種類を記録します。坐薬を使用した場合は、効果が出るまでの時間を、洗腸は投与した液の量を記録します。 |
| 投与時間 | |
| 食事の量 |
2024年1月
8分00秒
患者さんの排便状況は日々変わるのに、状態の把握がうまくできてない!その原因を探ってみるとどうやら記録の仕方にあるようで・・・



2025年9月作成

【第1回】排泄ケア、それは・・・
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第3回】排泄アセスメントの実際(1)
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第4回】排泄アセスメントの実際(2)
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第5回】排泄と食事の関係
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第6回】排便促進のポイント
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第7回】下剤に頼らない排便ケア-近森病院の取り組み① チーム発足-
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第8回】下剤に頼らない排便ケア-近森病院の取り組み② 多職種連携-
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生

【第9回】エコーによる排便アセスメント
【監修】日本コンチネンス協会 名誉会長/コンチネンスジャパン株式会社 専務取締役 西村 かおる 先生
本サイトでは、より良いコンテンツの提供、アクセス解析およびサイトの利便性向上のためにクッキー(Cookie)を使用しております。本サイトの閲覧を続けることで、クッキーの使用に同意したことになります。クッキーの設定変更および詳細についてはこちらをご覧ください。
